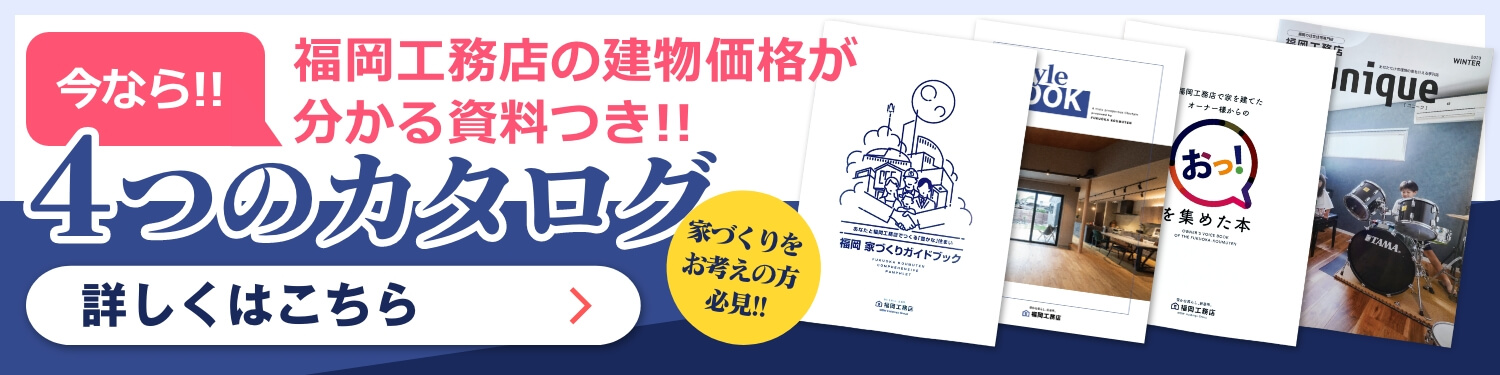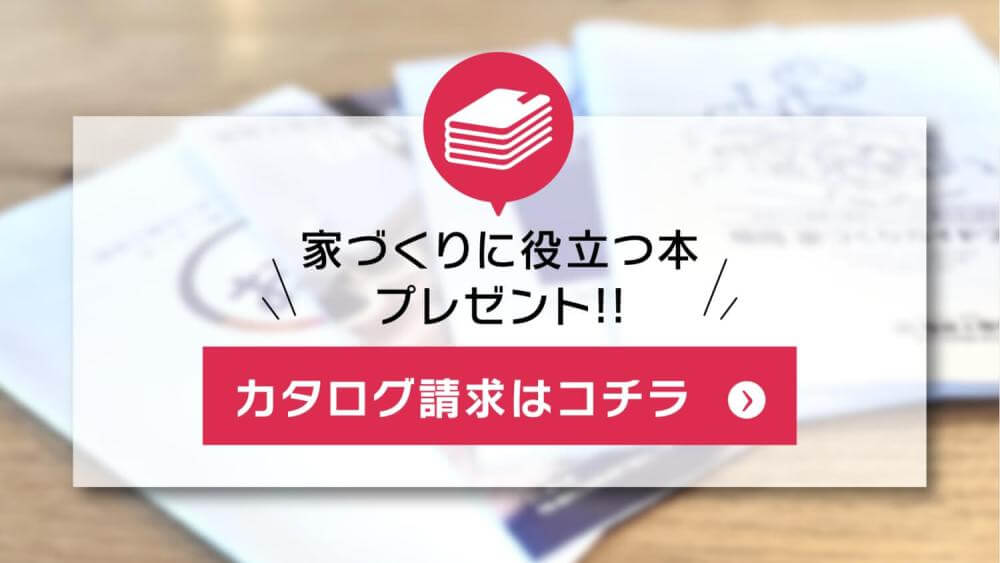「福岡市東区06」注文住宅現場リポート④【上棟式】
こんにちは。昨日、8月29日(木)福岡市東区にて上棟式を執り行いました。。朝は、雨に見舞われましたが、午後には回復し、大工職人、現場監督一丸となって、一気に工事を進めました。それでは早速、上棟式のリポートをさせて頂きます。▼午前7時30分。今回、上棟式をおこなう現場です。

▼午前7時40分。施主ご家族が現地に到着されました。棟梁土﨑大工がご挨拶をさせていただきました。

▼挨拶が終わったところで、早速「四方固め」です。工事が無事行われるように、塩、お米、お神酒で清めます。



▼工事が始まる前に、施主ご一家の益々のご繁栄と工事の安全を祈念して「乾杯。」です。


▼乾杯の後は、いよいよ上棟作業が始まります。大工職人が一斉に所定の位置に、柱を建てていきます。



▼柱を建て終わると、続いて梁や胴差しと呼ばれる横架材の設置が始まります。ラフタークレーンで横架材を持ち上げます。設置した横架材は、きっちりと柱にはまるように「かけや」と呼ばれる木槌で打ち込みます。。





▼大工職人たちの見事な技術と連携プレーで、梁の設置まで約1時間程で終わりました。続いて梁同士・または柱と梁を専用の金具で固定していく作業です。。




▼一方その頃、「建て入れ直し」が始まりました。立て入れ直しでは、柱に「下げ振り棒」と呼ばれる振り子がついた器具を柱に巻き付けて、垂直になっているかミリ単位で確認する作業です。。もし、少しでもズレている場合には、「屋起こし器」で調整していきます。。それぞれの柱がきちんと垂直になっているか一本一本確認していきます。。




▼1階の柱が全て垂直になったら、2階の合板を敷いていきます。。




▼合板敷きと並行して、必要な材料を上げていきます。


▼1階と同様に2階も梁と胴差を設置。手際良く作業をすすめていきます。。




▼午前9時30分。上棟スタートから1時間半でここまで進みました。ここから屋根の施工が始まります。




▼ここから屋根の施工が始まります。「小屋束」といわれる屋根を支える柱です。屋根の勾配に合わせて長さが違います。。




▼小屋束の上には「母屋」という横架材がかけられ、一番高い横架材を「棟木」と言います。棟木が取り付けられた時点で「上棟」を迎えます。。


▼小屋束と母屋には「かすがい」という金物が取り付けられます。

▼大工職人が声を掛け合い、母屋の通りが真っ直ぐになるよう施工します。。



▼屋根の施工が進んでいる最中、2階では泊大工と土﨑大工が、何やら作業を始められました。。



▼間柱部分の部材をカットされていたようです。後に施工されました。


▼屋根では、垂木の設置が始まりました。ここまでくると屋根の形が見えてきます。




▼現場監督の中村は、母屋の上に取り付けられた「垂木」との隙間に発泡ウレタンを流しこみます。。このわずかな隙間をふさぐことで外の暑さや寒さが室内に伝わることを防いでいます。。


▼垂木の設置が終わると、続けて外断熱材のキューワンボードを張ります。この断熱材には、銀色に光り輝くアルミ素材のシートが貼ってあり、遮熱効果があります。。





▼その後、キューワンボードを接いだ部分は、気密テープでふさいでいきます。。


▼キューワンボードの設置が終わると、上には、通気層を確保する「通気胴縁」の取り付けが始まります。。




▼2階の屋根の「通気胴縁」設置できたところで、昼食会です。お施主様、スタッフ、大工職人でお弁当をいただきました。。


▼昼食会の後に、設計士の朴と現場監督の小屋町が、図面と照らし合わせながら現場をご案内させて頂きました。。


▼休憩後は、上棟式で大工職人がおこなう最後の工事「野地板」の設置です。合板を運び、釘で通気胴縁に打ち付けます。。分担し、一気に作業を進めます。





▼余分な箇所は、その場でカットしていきます。


▼休憩後は、上棟式で大工職人がおこなう最後の工事「野地板」の設置です。合板を運び、釘で通気胴縁に打ち付けます。。分担し、一気に作業を進めます。





▼余分な箇所は、その場でカットしていきます。




▼屋根の施工が終わり、この後は屋根の防水処理のルーフィングに入ります。


▼ブルーシートで養生し、大工さんたちの作業は終了です。。

この度の上棟式、誠におめでとうございます。。これからも末永いお付き合いを宜しくお願い致します。。